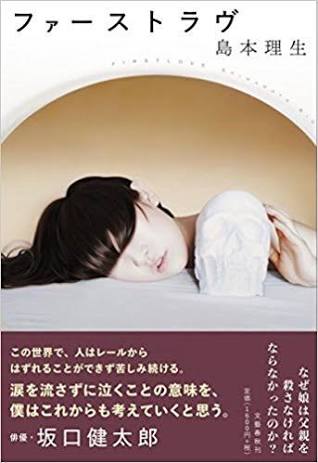あらすじ:ネタバレなし部分まで
臨床心理士の真壁由紀は、父親の殺人容疑で逮捕されたアナウンサー志望の女子大生・聖山環菜についてのノンフィクション作品執筆を依頼される。環菜は、取り調べをしていた刑事に「動機は分かりません。探してください」などと話していたのだという。
由紀は、環奈との接見や、元彼、母親、親友、父親が講師をしていた美術学校の生徒などに話を聞いていく。その中で、由紀の生い立ち、複雑な親子関係が徐々に明らかとなっていくのだった。由紀もまた、自分自身の過去と向き合い、裁判で「殺意の否定」を行い、父親が死んだのは「揉み合っている内に起こった事故」であると主張する。
由紀は、ノンフィクション本の執筆のための取材を行い、そして裁判の中での環菜の証言を聞くことにより、環菜の過去に何があったのか、その全貌が明らかとなるのだった。
あらすじ:ネタバレあり・結末まで
環菜は、12歳の頃に父・聖山那雄人によって美術学校の学生たちのためにモデルをさせていた。だが、環菜にとってそれは長時間、男性ばかりの視線を受け、緊張感を強いられることだった。また、全裸の男性と一緒にモデルを務めることもあり、それも環菜にとっては精神的負担を強いられることだった。さらには、生徒の中に体を触ってきたり、酔って抱き着いてくる生徒もいた。環菜は精神的にストレスを感じていたのだが、父親の命令であり、断ることはできなかった。
さらには同時期、父親は飲み歩いて鍵をたびたびなくしていたため、「玄関のドアに鍵をかけるな」と命じていた。だが、家に一人だけ留守番していたこともあり、環菜は鍵をかけて眠ってしまった。帰宅した父親は激怒し、環菜を家から追い出した。
行き場のなかった環菜は街で転んでしまい、そんな時に声をかけたのがコンビニ店員の小泉裕二だった。小泉は環菜を家に連れていき、一晩泊めることになった。小泉は12歳ながら環菜と関係を持とうとし、環菜は応じるしかなかった。このことをきっかけに環菜は、「美術学校の生徒たちの目線や、体を触れられ、抱き着くといったこと」が性的なことであると理解する。
さらに、父親が命じるモデルになることが苦痛となった環菜は、リストカットなどの自傷行為をするようになる。その傷を見た父親は、「そんな傷があったらモデルはできない」と、休ませるようになる。そのため、環菜はモデルとなることを避けるため、日常的に自傷行為をするようになる。
母親は、環菜が年上の男性に性行為をさせられていたこと、そして自傷行為にうすうす気づきながらも、見て見ぬふりを続けていた。環菜はその後も、自傷行為を繰り返していた。
環菜は大学へと進学し、アナウンサーとなることを志望していた。ところが、父親はそのことに反対していた。環菜は、それでもキー局のアナウンサーとなるべく挑み、二次面接まで進んだ。
ところが、その二次面接での「男性ばかりの中、視線を一身に浴び、すさまじい緊張感を感じる」という状況は、まさに父親が強いた「デッサンのモデル」と同じものだった。そのため、環菜は体調不良を訴え、倒れてしまう。
試験に失敗した環菜は、帰りに包丁を購入する。その包丁は、リストカットを行うためのものだったのだ。環菜は「血を流すことで苦痛から逃れたい」と思い、自らを傷つけた上で父親がいる美術学校を訪れ、その様子を見せようとした。
だが、父親は「お前がおかしくなったのは、母親の遺伝だ。母親に責任を取らせる」と言い、母親に電話をしようとする。環菜は、母親にリストカットのことを知られたくないと思い、スマートフォンを奪おうとするが、そこでもみ合いとなり、包丁が胸に刺さって父親は死亡した…というのが事件の全容だった。
その後、環菜は帰宅し、母親にそのことを告げるも、母親は環菜のことを責めるばかりだった。環菜は行き場を失い、河川敷を歩いているところを発見され、逮捕されたのだった。
由紀は、環菜が過去と向き合い、堂々と裁判所で被告人として証言できたことを好ましく思う。弁護側は、成人男性ばかりが一斉に視線を向けるモデルを強いられたこと、全裸の男性とモデルをさせられたことは性虐待にあたり、人格形成に大きく影響を及ぼしたこと、そして環菜には殺意はなく無罪であると最終弁論で主張するのだった。
由紀は、環菜の母親も過去に性虐待を受けていたことに気づく。そして、環菜と同様に自傷行為をしていた。母親もまた、性虐待に苦しみ、過去に蓋をするように、環菜の苦しみを見て見ぬふりをしていたのだった。由紀は彼女に「しかるべき医療機関でご相談を」と勧めるのだが、「私は正常よ」と言うだけであった。
判決が下り、環菜は懲役8年の刑を言い渡される。環菜はそれを受け入れる。結果、事件への関心は急速に薄れ、ノンフィクション作品出版は中止となる。代わりに、辻編集者から「女性の性被害を特集したノンフィクション作品を書いてはいただけませんか」と提案され、環菜は受け入れるのだった。